【企業選びの時期】
12月になりアルバイト先の学生から就職活動に関する話を聞くようになった。私も定番とばかりにリクナビに登録した。リクナビには生年月日を入力する欄がないためか、特に年齢でフィルタリングされることもなく、企業から次々とDMが届いた。
新卒の就職活動についていろいろと調べていると、「リクルートエージェント」という就職先を紹介してくれる会社があることがわかった。早速登録することにした。数日後、担当者から電話がかかってきて、いろいろと質問された。履歴書のような書類を提出し、紹介を待つことにした。
私の学科では、学科推薦制度を使う人は学科の就職相談室を通して就職活動をすることになっていた。事前に志望する業種や企業などを書いた書類を提出しておき、グループ面談や個人面談を行い、推薦で応募する企業を決める。
私は医療機器の回路設計の仕事に興味があったので、その分野を第一志望にしていることを就職担当の教員に伝えた。特に反対されることもなく、「企業研究を進めるように」という指示を受けた。就職担当教員や相談室の事務補佐員の方の話では、「推薦制度がある企業は自由応募ではまず受からない」とのことだった。私のような特殊な学生は、自由応募で受かるとは考えにくいので企業研究、社会勉強として自由応募で活動を続けつつ、推薦での採用を目指すことにした。

【推薦企業決定】
私が最も興味を持っていたのは「アロカ」という老舗の医療機器メーカーだった。しかしこの企業は学科に推薦が来ないということがわかり、自由応募で応募することになった。そこで同業の他社を探したところ、「日立メディコ」という日立製作所の子会社で画像診断装置を開発している会社があることがわかった。幸い、過去に同じ学科からの採用実績があり、推薦が来るということだった。ところが、この会社は学科推薦という制度は存在しておらず、推薦書を添付することで推薦扱いとなることがわかった。しかもエントリーシートが研究経歴を深く追求するものであり、私の経歴ではどうしても書きにくかった。そんな状況の中、日立製作所の分社化子会社である「日立ハイテクノロジーズ」(以下、通称の日立ハイテク)という会社が医療用の分析装置を開発していることがわかり、興味を持つようになった。しかも、この会社は分社化したばかりの子会社であり、日立製作所のジョブマッチングによる推薦制度が使えるということもわかった。自分の中で「日立ブランド」というのは非常に魅力的だったので、迷わずこの会社を第一志望とし、日立製作所の推薦枠を取得することを目指した。
就職相談室の事務補佐員に日立製作所のリクルータを紹介していただき、メールで連絡を取り、リクルータに会いに行くことになった。
リクルータと志望する部署を決める話し合いを行い、医療用分析装置を開発している茨城県ひたちなか市の那珂事業所を選ぶことになった。
【事業所見学】
日立製作所のリクルータから日立ハイテクのOBを紹介してもらい、その方とメールで連絡を取りながら、事業所見学の日を決めた。
所要時間2時間、久しぶりに特急に乗った。駅を降りるとのどかな田舎町へ。指示されたとおりタクシーに乗り、工場正門までやってくる。名前を告げると、正面玄関に行くように言われる。正面玄関に行くと、部屋に通される。人事の人と一対一だった。わざわざ1人のために、パワーポイントで説明をしてくれた。その後、OBを含む技術者3人にそれぞれ担当の部署を案内してもらう。その後、質問時間を十分に取ってもらう。途中から、雑談ぽくなり社員同士が話を始める。社内の大学院進学制度についていろいろ質問していたら、「もう一度大学院に進学するか就職するか考えたほうがいい」と、ちょっと痛いことを言われる。今後、大学院のことは一切口に出さないことに決めた。お茶とコーヒーをご馳走になり、帰りはタクシー代も出してもらった。何と待遇のいい会社なのだろうか。仕事内容も自分の興味とぴったり一致していた。
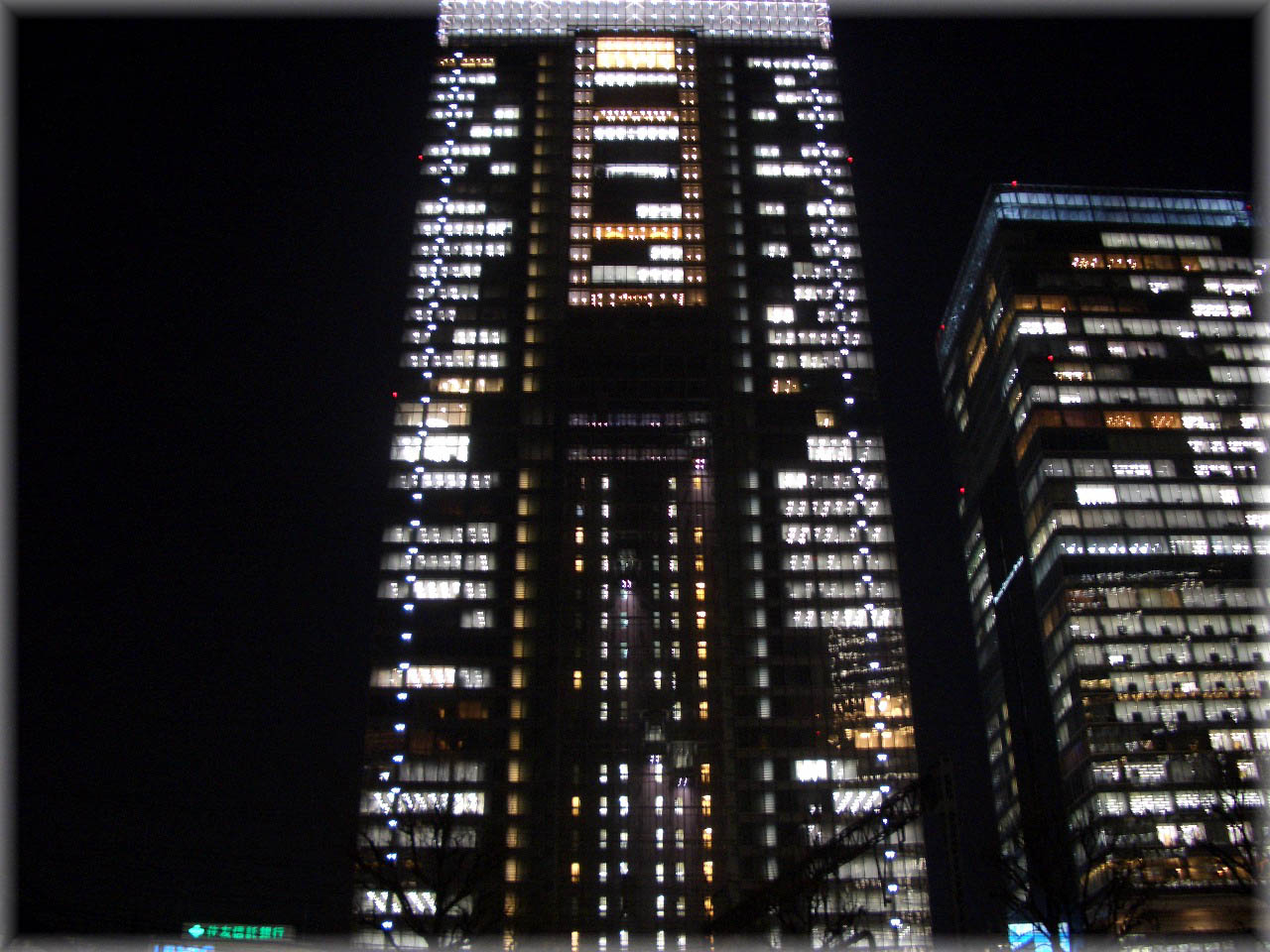
【入社試験】
推薦枠4名に対し、応募者4名ということで、無事に日立製作所の推薦枠を取得した。リクルータから紹介されたエントリーサイトにアクセスし、研究内容や経歴などを入力し、予定通り、事業所見学を行った事業所に応募した。
指定した日に一次面接に行ってきた。参加者は2人。1人は筑波大学の学生ではないかと思われた。午前中は事業所見学だった。午後から面接だった。人事はいない面接のためか、終始和やかな雰囲気だった。経歴、志望動機、研究内容、志望職種などごく普通のことを聞かれた。言うべきことは全て言えた。結果は一週間以内には出ると言われた。今回も交通費は全額支給だった。
【採否】
結果はあまりにも早く出た。入社試験から帰宅後、試験の手ごたえなどをお世話をしていただいたOBに書いたあと、エントリーサイトにアクセスしたところ「ジョブマッチング不成立」、すなわち不採用という結果が出ていることがわかった。
自分では面接の出来に満足していただけに残念である。また、いろいろとお世話をしていただいたリクルータやOBには本当に申し訳ないと思った。
落とされた原因は、私が特殊な経歴を持っていることや年齢が高いことではないということを後日OBから知らされた。
試験を受けた後に知ったことだが、日立ハイテク那珂事業所は、数年前に日立製作所の計測器事業部から分社化した会社で、今でも日立グループの稼ぎ頭である。社員の平均年収は日立製作所をはるかにしのいでいる。また、研究開発に力を入れていることもあり、大卒者よりも大学院卒者を多く採用している。卒業研究を履修していなかった私は、研究能力が劣っているとみなされてしまったのが敗因ではないかと考えた。
思い入れが強かったので、落胆も大きかったが、思い悩んでいる時間的な余裕もないので、すぐに次の応募先を考えることにした。
【自由応募】
学科推薦での活動と平行して、いくつかの会社に応募していた。一次選考を通過した会社はいくつかあったが、どうしてもその先には進めなかった。当初、第一志望としていた「アロカ」からは書類を送付したものの連絡が来ない、すなわち門前払いとなり、「日立メディコ」はエントリーシートが書けずに断念していた。
【推薦企業決定その2】
日立製作所のジョブマッチング制度は推薦枠1つにつき、3つの事業所まで応募できることになっている。日立ハイテクに不採用となった私も、日立製作所の事業所および分社化子会社の事業所にあと2箇所まで応募できた。この段階では、当初の志望だった医療機器の回路設計という職を諦めなければならないと思うようになっていた。医療機器の次に興味がある通信機器や産業機器の回路設計の会社に応募してみようかと思うようになっていた。日立製作所および分社化子会社にはそういった事業所がいくつかあったので応募を考えて企業研究をすることになった。そこで興味を持ったのが、「日立産機システム」という会社だった。応募するかどうか決めかねた段階だったので、リクルータに仲介を頼まずに自分で連絡を取って事業所見学に行った。千葉県習志野市にあるこの会社は、数年前に日立製作所から分社化した会社であり、どことなく工場の雰囲気が日立ハイテクに似ていた。採用担当の方は非常に親切だった。かなりいい印象を持ったのだが、「同じ日立グループの会社に応募しても同じ結果になるのではないか」という不安と、日立ハイテクへの思いを引きずった状態で同じグループ会社に応募することに抵抗があったので、応募せずに別の推薦企業を探すことにした。
幸い、日立製作所のジョブマッチング制度は、応募していない状態では推薦扱いにはならないので、他の企業に推薦で応募することができた。
自由応募での応募を考えて工場見学を行っていた電機メーカーで興味を持っていた会社があった。学科の就職相談室に行き、その企業の推薦枠があるかどうかを確認したところ、「推薦枠は埋まっているが+αで応募できるかもしれない」とのことだった。就職担当の教員に確認してもらったところ、「応募できる」と言われた。早速、推薦書をお願いし、応募することにした。日立製作所のリクルータにもこの状況をきちんと伝えた。
【入社試験その2】
推薦で応募する某電機メーカーの書類を作成した。履歴書、自己紹介、研究内容、推薦書、送付状を入れて封をする。推薦で応募するのは2社目ではあるが、1社目は推薦書提出前に敗退となってしまったため推薦書を送付するのは初めてとなる。もうすぐ5月になり、そろそろ半数程度の学生も内定が出ている状況だった。「自分の能力を信じて」というよりも「推薦書の効力を信じて」という心境だった。
書類を送付して数日後、一次面接の日時を知らせる電話がかかってきた。「明日面接を行うので来てほしい」という内容だった。
夕方からという変な時間の面接だったため、アルバイトを早めに切り上げて会社に向かった。入ると誰もいない受付にテレビ電話みたいなものがある。その隣に「面接の方は奥のテーブルでお待ちください」と書かれていたので電話はせずに待つことにする。しばらくすると隠しカメラがあるのだろうか、人が出てくる。時間はまだあるのに、「早めに始めます」とのこと。鞄も持ったまま面接室のドアをノックし中に入る。挨拶をして椅子に座る。面接官は4人(進行役の事務員1人、技術者3人)だった。最初は進行役の人が志望動機を質問し、その後、技術者が技術的なことを質問してきた。ごく普通の面接という感じで30分程度で終了した。ただし、少し面接官が退屈そうなのが気になった。

【内々定】
推薦で応募していた某電機メーカーの面接を受けてから2週間が経過しても連絡がないので、学科の就職相談室に行き事務補佐員に相談をした。就職担当の先生も心配していたようで、あとで先生が電話して確認するということになった。先生が授業をしているということで、しばらく待つことに。今までの経験から連絡が遅いときはだいたいだめなので、「どうせだめだろう」と諦め、次に応募する候補の企業の求人票をコピーしたりしながら待った。コピーした企業は印刷業界大手の大日本印刷、重電5位の明電舎だった。手持ちの日立製作所のジョブマッチング制度で応募できる2社と比較検討しながら応募する企業を決めるつもりだった。しばらく待っていると先生がやってきて、まずは他の学生に内定の連絡を入れるなどの作業をする。その後、私の件に取り掛かり、まずはリクルータに電話をする。こんな話が聞こえてきた。「本人に知らせていいの?」「じゃあ連絡を取って」。その後、人事から相談室に電話が来るということになり、10分程度待つ。待っている間に先生は別の学生の応募企業選びを手伝っている。今、企業選びをしているということは、私と同様に推薦企業に落ちて、次を探しているということだ。そんな光景を見ながら、今までの就職活動を振りかえっていた。「この年齢だし常識で考えたら内定なんてもらえるはずない」「もしかしたら内定をもらえるかもしれない」などいろいろな考えが頭をよぎる。すると電話が鳴り、事務員が出て、すぐに先生に代わる。先生が「ありがとうございます」といった瞬間、近くにいた事務補佐員が手で ○の合図をする。先生が電話を終える「内定だぞ、おめでとう」と握手を求めて私のほうへきて握手をして「ありがとうございます。先生のおかげです」と言う。その間、事務補佐員は拍手をしていた。一方で、少し居心地が悪そうにする推薦企業に落ちて応募企業選びをしていた学生が視界に入る。私はうれしいという気持ちの一方、少し心苦しくなり、早々と退出した。
平成19年5月11日(金)、私の就職活動は終わった。

【就職活動の結果】
◎(推薦)某電機メーカー・・・1次面接採用
×(推薦)日立ハイテクノロジーズ・・・1次面接敗退
×(自由)オリンパス・・・SPI敗退
×(自由)ケンウッド・・・書類選考通過、1次面接敗退
×(自由)新キャタピラー三菱・・・SPI通過、1次面接敗退
×(自由)東芝システムテクノロジー・・・筆記試験・書類選考敗退
? (自由) 東芝電力系統システムテクノロジー・・・書類選考敗退
×(自由)東芝テリー・・・書類選考通過、1次面接敗退
×(自由)テクノメディカ・・・書類選考敗退
×(自由)アロカ・・・書類選考敗退
×(自由)日立ビアメカニクス・・・書類選考敗退
×(自由)昭特製作所・・・書類選考敗退
×(自由)アツデン・・・書類選考通過、一次面接敗退
? (自由) ニコンシステム・・・書類選考通過後、都合により受験断念
【感想】
私のような学士入学者が就職活動を行うにはそれなりの覚悟と勇気が必要だと思う。企業から年齢差別、経歴差別などの差別を受ける可能性は否定できないからだ。私も当初は、活動を行うことに大きな不安を持っていたが、活動を進めるにつれて、「自分が気にしているほど企業側は気にしていない」ということがわかった。大きな企業ほど私のような特殊な人にむしろ興味を持ってくれていた気がする。推薦で日立製作所の分社化子会社である日立ハイテクの一次面接で落ちた後、親切にもらっていたOBの方から「人事に確認したところ、経歴はむしろ評価されていて年齢による差別はなかった」という内容のメールをもらった。自分が差別されていないこと、経歴が評価されていたことを知って本当にうれしかった。その一方で、書類を送っても連絡が来なかった企業、成績証明書を開封もせずに返送してきた企業もあった。ただ、こういったことは、学士入学者以外であっても起こりうることなので、「差別」だったのかどうかはわからないままである。
私が内々定をもらったのは、5月11日。この時期、同じ学科ではまだ半数程度の学生は活動を続けていたので、単純に決まった日だけを考えれば、早くもなく遅くもなかった。
結論として言えることは、特殊な経歴を持っていても年齢が多少高くても、それを負い目に感じずに普通に活動をすれば必ず結果は出るということだ。
【信念】
就職活動をする上で一つの信念を持っていた。それは、「学業を犠牲にする活動は一切しない」ということだ。最初の大学生だったころ、授業を休んでまで就職活動をし、早々と内定をもらい他の学生に自慢しているような学生が少なからずいた。その様子を冷ややかな目で見て、「あのようなことは絶対にやりたくない」と思ったものだ。「学生の本分は学業であり、就職活動ではない、学業を犠牲にしてまでして得た内定に価値はない」と思い続けていた。当時、二部ではなく一部の学生だった私が、本格的に就職活動を始めたのは前期の授業が終わる7月下旬になってからだった。
それから数年、年齢を重ねてもその信念を変えることはなかった。二部学生だったため、活動はしやすかったが、授業の時間に間に合わないため応募を断念したこともあった。信念を貫いたことは間違っていないと思っている。
